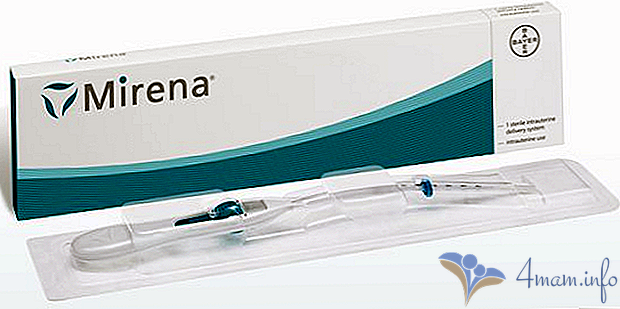キッチンだけでなく、直接出会う厨房機器のおそらく唯一の代表が、また、例えば、オフィスで - - エレクトリック多くの人々が一日の開始前に、お茶やコーヒーカップを応援するのが大好きですので。飲み物なしで当日にならないためには、私たちの多くは、大幅にその準備を簡素化します電気を購入することを決定しました。
1年以上私たちに役立つ電気ケトルを選択すると、それぞれが製品の動作における信頼性、安全性、快適性に影響する多くの特性に左右されます。スパイラルまたはディスク - ケトルの中で最も重要な要素は、その発熱体です。加熱下螺旋要素は、水と直接接触しています。その製造鋼のために使用される - 以下の実用的なステンレス又はクロム。渦巻きは水を比較的ゆっくりと加熱し、すぐにスケールの層で覆われ、少しの水を加熱することができません(これは焼損に悩まされています)。螺旋部材の利点は、それがインストールされている低価格の電気釜、また、低ノイズと呼ぶことができます。
あなたはあまりにも多くの時間を待って、電気のために支払う必要はありません - ディスク状の発熱体は非常に便利である任意の量の水を、加熱することが可能です。ディスクは水に触れることはありませんが、ステンレススチールで作られていますので、スカムとの戦闘ははるかに簡単です。発熱体の保護のおかげで、電気ケトルは螺旋状のものよりもずっと長く持続しますが、このための価格はわずかに高い騒音レベルになります。
ケトル内の水の純度は、注ぎ口に取り付けられたフィルターによって提供される。フィルタの主な要件は、良好な浄水、除去の容易さ、設置および洗浄、ならびに大きな濾過領域である。フィルタの製造には、金属、プラスチック、ナイロンを使用した。
ケトルの建設の義務的な要素は、ガラスまたはプラスチック製の透明なインサートでなければならず、水面に印がついていなければなりません。より利便性を高めるために、それらの2つが存在することが望ましい。電気ケトルのカバーは、火傷を避けるためにボタンを押したときにのみしっかりと閉じて開けなければならず、注ぎ口がはっきりと突出していなければなりません。
ケトルの容量は容量と相関しています。水が熱くなればなるほど、この数値は大きくなるはずです。現代のティーポットは、1リットルから2リットルの水まで加熱できますが、消費電力は1〜3kWです。水が通常よりも速く熱くなりたい場合は、もう少し強力なティーポットを買う価値がありますが、電気ネットワークの可能性を考慮してください。
水が通常より速く熱くなるようにするには、もう少し力を入れてティーポットを買うべきですが、電力網の可能性を考慮してください
大部分の場合に電気炉を製造するために、プラスチック、金属およびガラスの3つの材料が使用される。プラスチック製のティーポットは最も安価で一般的なので、家電店で購入することができます。彼らは様々な住宅のバージョンと色のソリューションで利用可能ですが、あまり実用的ではありません - このタイプの表面は汚染されやすいです。メタル製のボディは、艶消しとクロームバージョンで提供されていますが、スタイリッシュに見えますので、すばやく汚れることはありません。単一のケースの金属製電気ケトルは、特殊な強度と信頼性が特徴です。ガラス製の電気ケトルは、一般的ではなく、取り扱いにはあまり実用的ではありませんが、エレガントに見え、水の味を変えません。専門家は、このようなティーポットを使用して作られたお茶は、金属製またはプラスチック製のアナログ製作に使用されるものよりもずっと美味しいと言います。
電気ポットや他の家電製品を購入する際の主な基準は、その安全性です。多くの場合、品質の悪い機器が大規模な火災を引き起こしました。水が沸騰し、さらに自動切断装置は、このような火災に対する加熱カバーが開いているときに切り換え素子、並びに保護を防止するロックとしてケトル機能を有することが望ましい - ない水が存在しない場合、それは自動的にデバイスをオフに切り替えます。多くの場合、電気ケトルには、沸騰水の音信号を報告する機能と、ネットワークへの接続を知らせる光の表示があります。
それがプラスチックである場合、すべての項目が確実に固定しなければならない、と材料 - - 購入する際に長い、彼らの信頼性を喜ばせるために慎重に検査しますケトルを選択するには悪臭をしないように。また、売り手に国と製造業者について尋ねるのをためらうこともありません。疑いがある場合は、製品のドキュメントを提示するように頼みましょう。